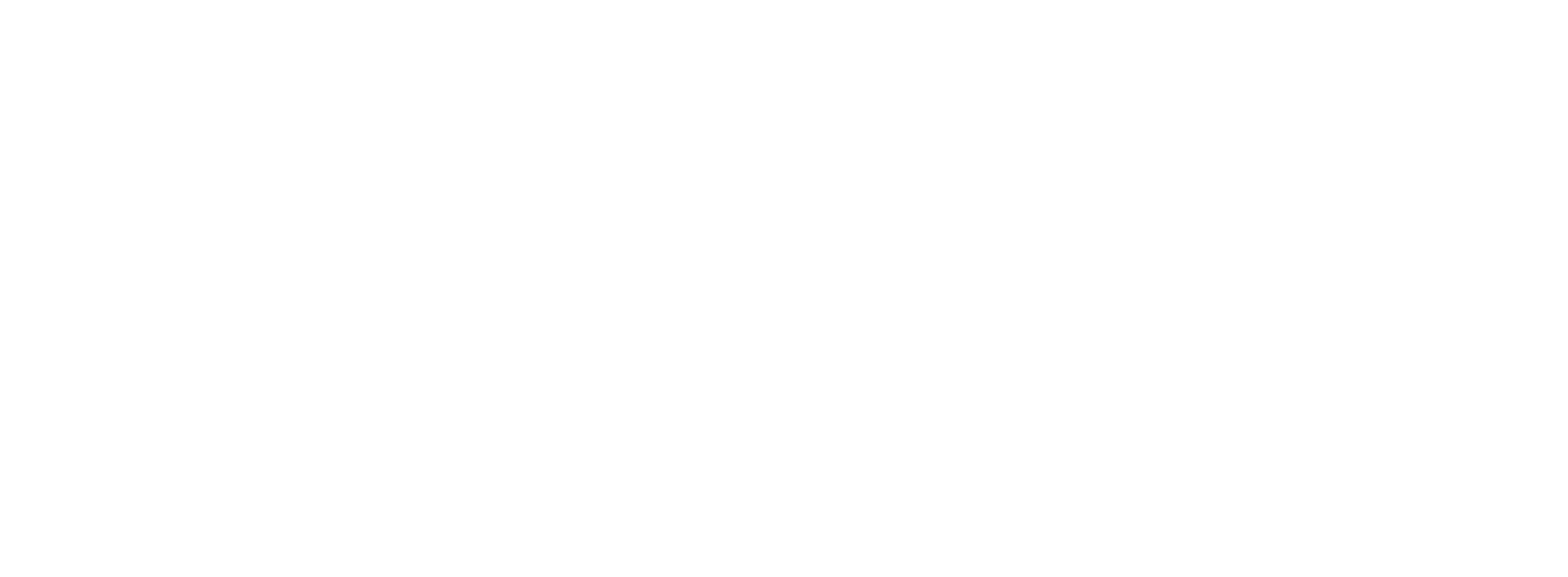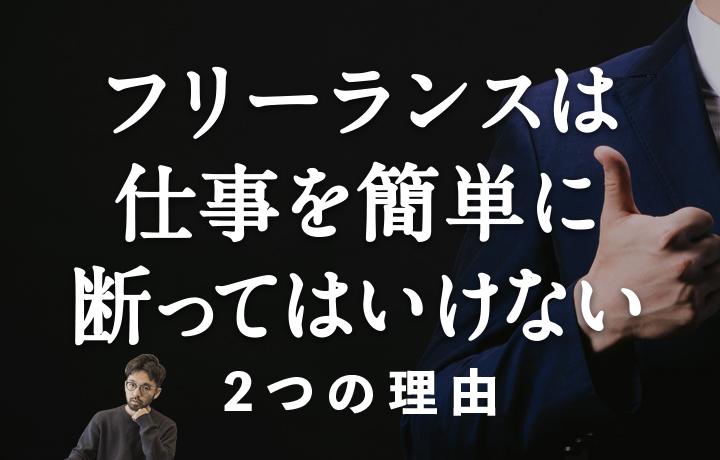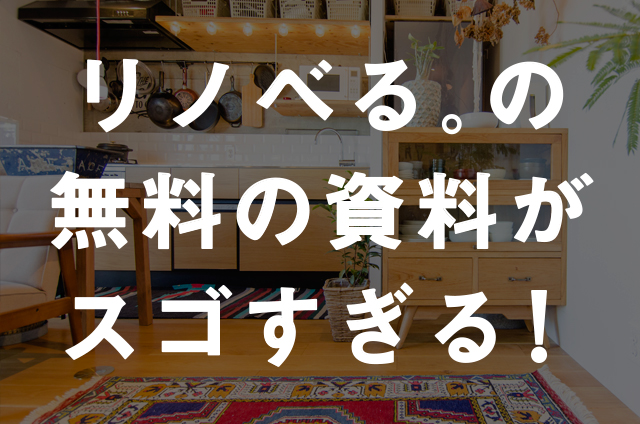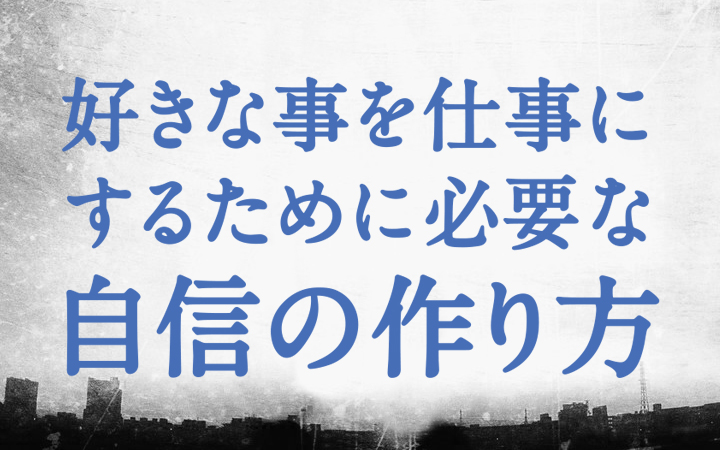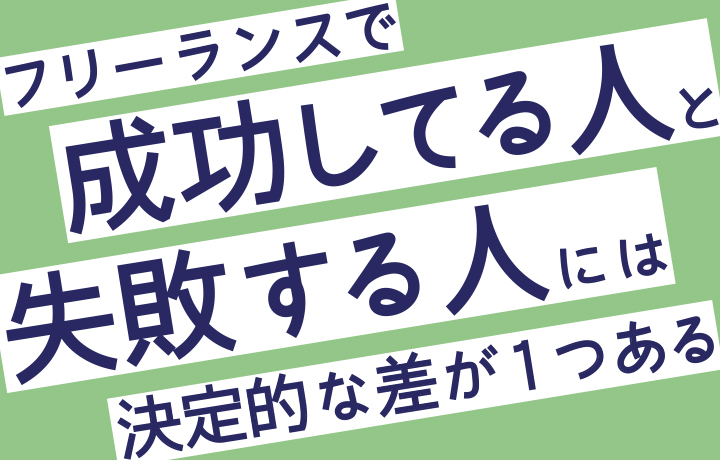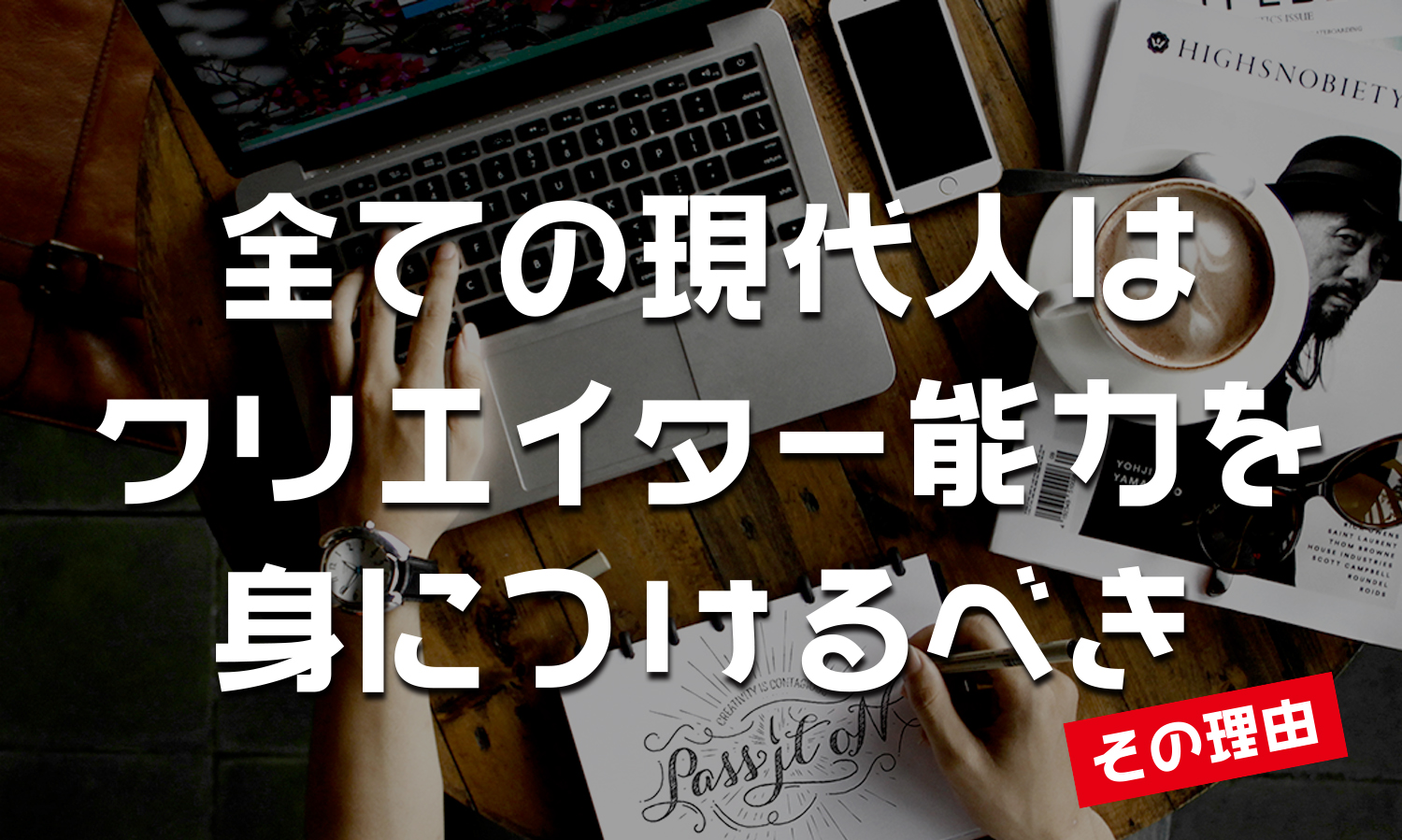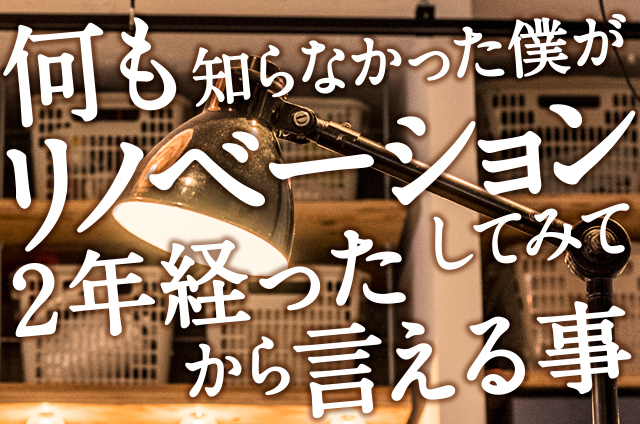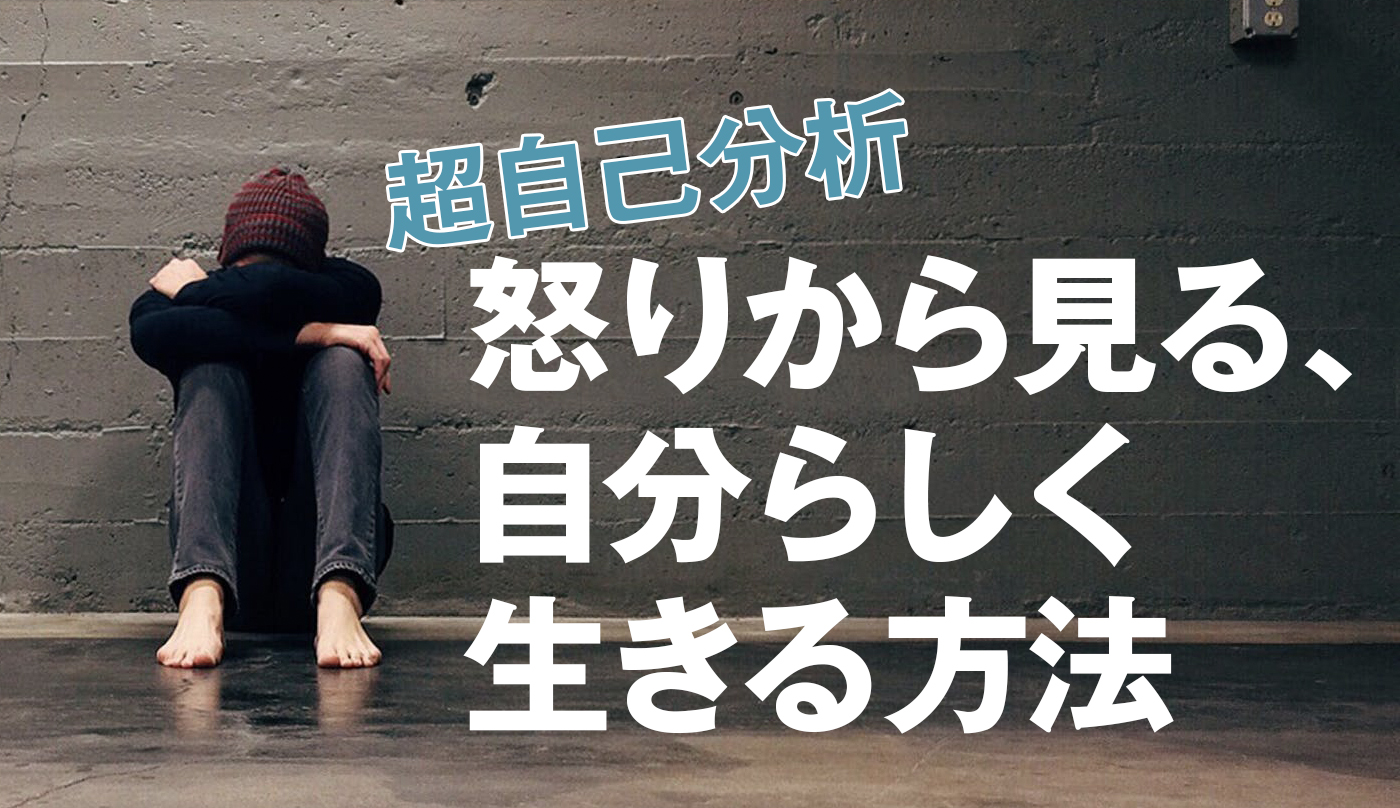好きな事を仕事にする方法は需要の流れをデザインしなければいけない

こんにちは。自分の好きな事(インテリア、デザイン、一眼レフカメラ)を仕事にしている崇島亮です。
僕は会社を辞めて現在はフリーランスとして好きな事だけに絞って仕事をしています。
誰でも好きな事をだけをして生きていきたいと思うのは自然なことですが、実際そうやって生きるにはハードル高いように思っていませんか?
そこで好きなことだけで生きるためには何が必要なのか考えてみました。
キーワードは『価値』と『需要』です。よくビジネスチャンスを海(オーシャン)に例えますが、僕は好きな事を仕事にする事は、何もなかったところから水源を作り海(オーシャン)へ向かって流れる川のルートを如何にデザインする事なのだと思っています。
ルートをデザインして水源を海へ送ること
僕は趣味や好きな事を仕事にする場合、各個人によってやり方は全く異なり、これをやっていればいいというような正攻法は無いです。なぜなら、全く同じパーソナルを持った人間がいない、さらに趣味や好きな事は極めて個人的なもので、誰かのやり方をトレースしたところで自分の能力との相違が出てくるからです。一人一人の個性が違うように成功の道もそれぞれ異なってくるというわけです。
ただし、基本的な考え方は同じです。
経済の基本的な構造は、自分が持つ『価値』と相手の『需要』で決まってきます。これは誰にでも当てはまる事で、仕事は経済活動ですからこの構造を無視する事は出来ません。
趣味や好きな事を仕事にする事の難易度が高く感じるのは、前例がない事と趣味や好きな事となると自分のこと過ぎて客観視できないことで『需要』が見えにくくなっている状態が原因です。
だから、闇雲にスキルを磨いたり、人脈を広げることよりも全体の構造を理解して自分が今どこに注力して行動すればいいかを考えるべきです。頑張っていればいつか報われるというような非効率な賭けをしていても成功は訪れないでしょう。
全体の流れを考えて、まず自分の価値を『水源』として、仕事になるための需要を『海』と例えてみましょう。そうすると如何にして『川』を作るかがカギになってくると想像できるはずです。
では、僕が実践している『川』のルートの作り方について説明してみましょう。
1、対象
何をやりたいのか?という自分の水源に対して、誰にという『対象』を明確にすること。最初の方向性を考えます。
これがスタートです。
2、問題
次は、その対象について考えます。
相手は何を考えているのか?何が好きで何が嫌いなのか?ライフスタイルとライフサイクルはどうなっているか?その中でターゲットが困っている事や満ち足りていない事などのインサイトを見つける作業をします。
インサイトというのは消費者の行動や思惑、その背景にある意識構造を見ぬいたことによって得られる「購買意欲の核心」のことです。
3、商品・サービス(価値)
ターゲットの問題に対して自分が出来る事や叶えられる『価値』を用意します。
つまずきやすいのが、この部分で、自分が最高だと思っている商品やサービスを用意してしまいがちなのですが、それでは単なる自己満足になってしまいます。
4、解決
用意した商品やサービスが仮説通り実際に解決できているか?を確認します。解決できない、足りていないようなら出来るまでブラッシュアップを続けます。
5、市場
ここからはプロダクト(商品やサービス)からセールスのフェーズに入ります。
自分が用意した商品やサービスには、どれだけの可能性を持っているか?市場規模を調べて最初に決めた想定ターゲットが世の中にどれだけいるのか?
勝負できる市場規模ではないのなら初期設定のやり直しです。勝算のないチャレンジをしてはいけない。
6、文化
自分の好きな事をする場合に意外と大事な事なのが、受け入れられるのかどうか?というところです。
例えば、皆さんが日常的に使っている電車の乗り換え時刻が分かるスマホアプリは、時間を守る日本の鉄道会社だから成立するサービスです。時間を守る『文化』がある日本だから多くの人に使われているわけです。
理論上いいものでも上手くいかない場合があります。
7、位置
成功するために必要な最後の要素は『位置』です。言い方を変えるとターゲットに対して正確にリーチする事です。
ターゲットを設定してその相手にピッタリな価値を用意してビジネスとしての勝算があったとしても、その価値を置く場所を間違えたら効果は期待できません。
自分の相手がどこに集まっているのか、または集まる場所を作っておくのか、どんな形でもいいから『位置』を見極めて自分が持つ価値をピンポイントに置く必要があります。
ここまで来ると他者が簡単には真似する事は出来ません。その先にはまだ誰も知らない自分だけのニューオーシャンが待っているのです。
そしてこれを考えて行動し、もし良い結果が得られなかった時でも順を追って何が悪かったかを振り返られるので軌道修正もやりやすくなります。
というわけで、まとめると
- 対象(ターゲット設定)
- 問題(シーズ分析)
- 商品・サービス(提供価値)
- 解決(ニーズ)
- 市場(規模分析)
- 文化(整合性)
- 位置(リーチ)
この順番で考えてみると、水源から川のルートをデザインする事でき、海までたどり着くことができるのです。
そのルートは人それぞれ全く異なり、
【水源の大きさ】×【ルートの設計】=【ニューオーシャン】
というあなただけの方程式が完成するのです。