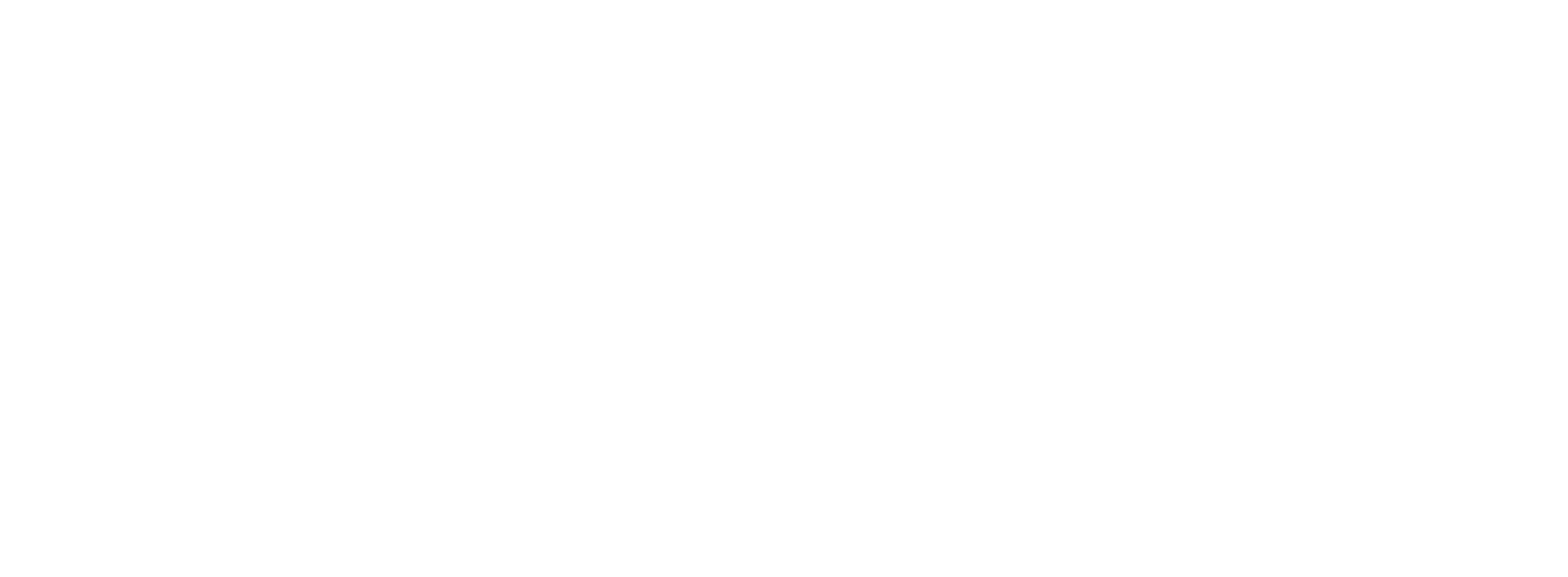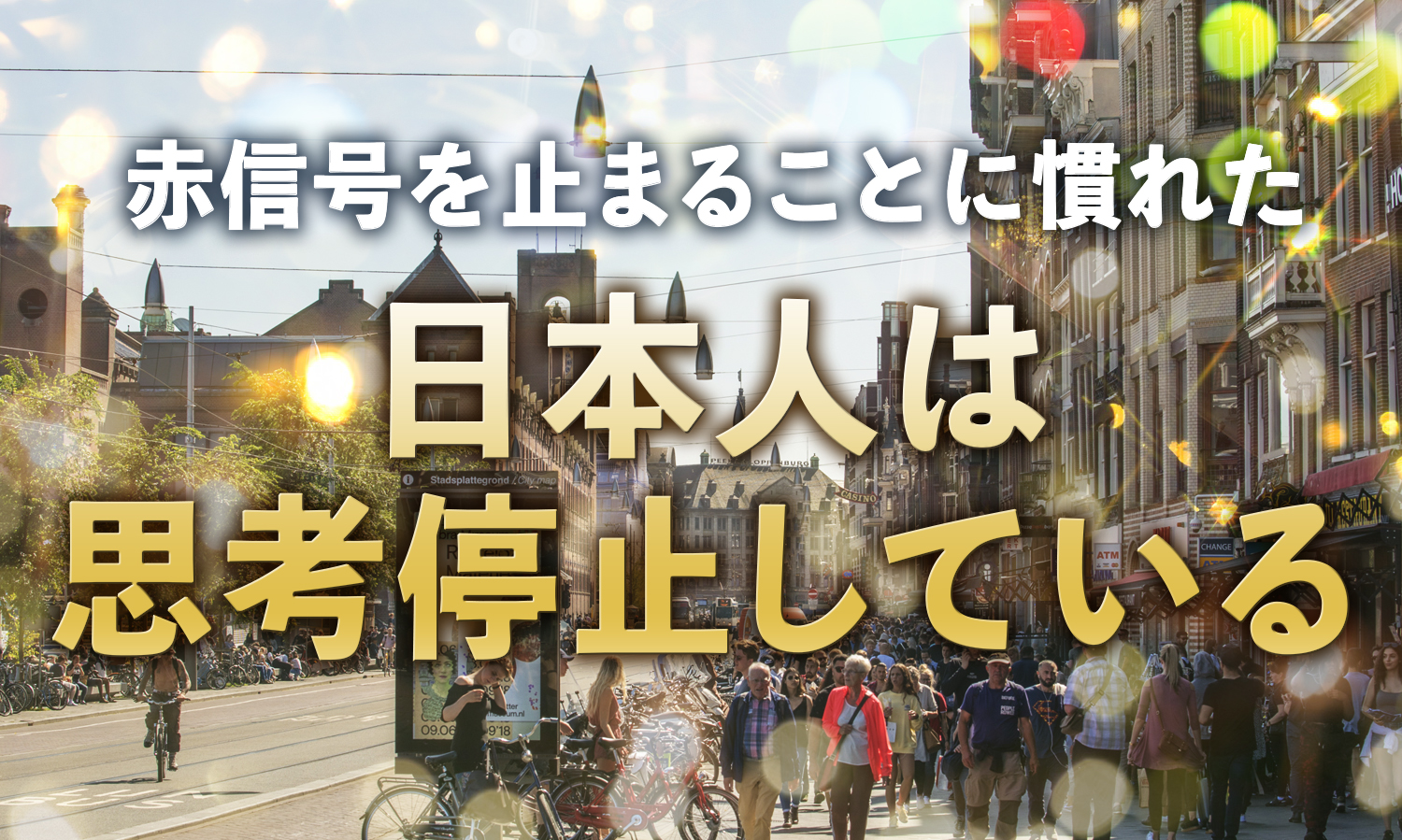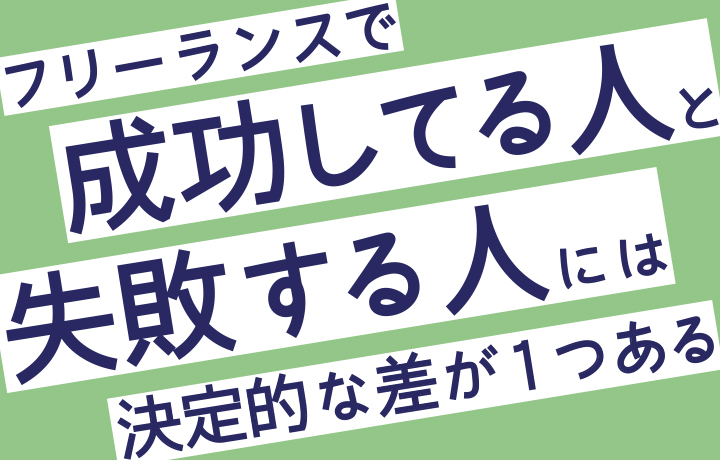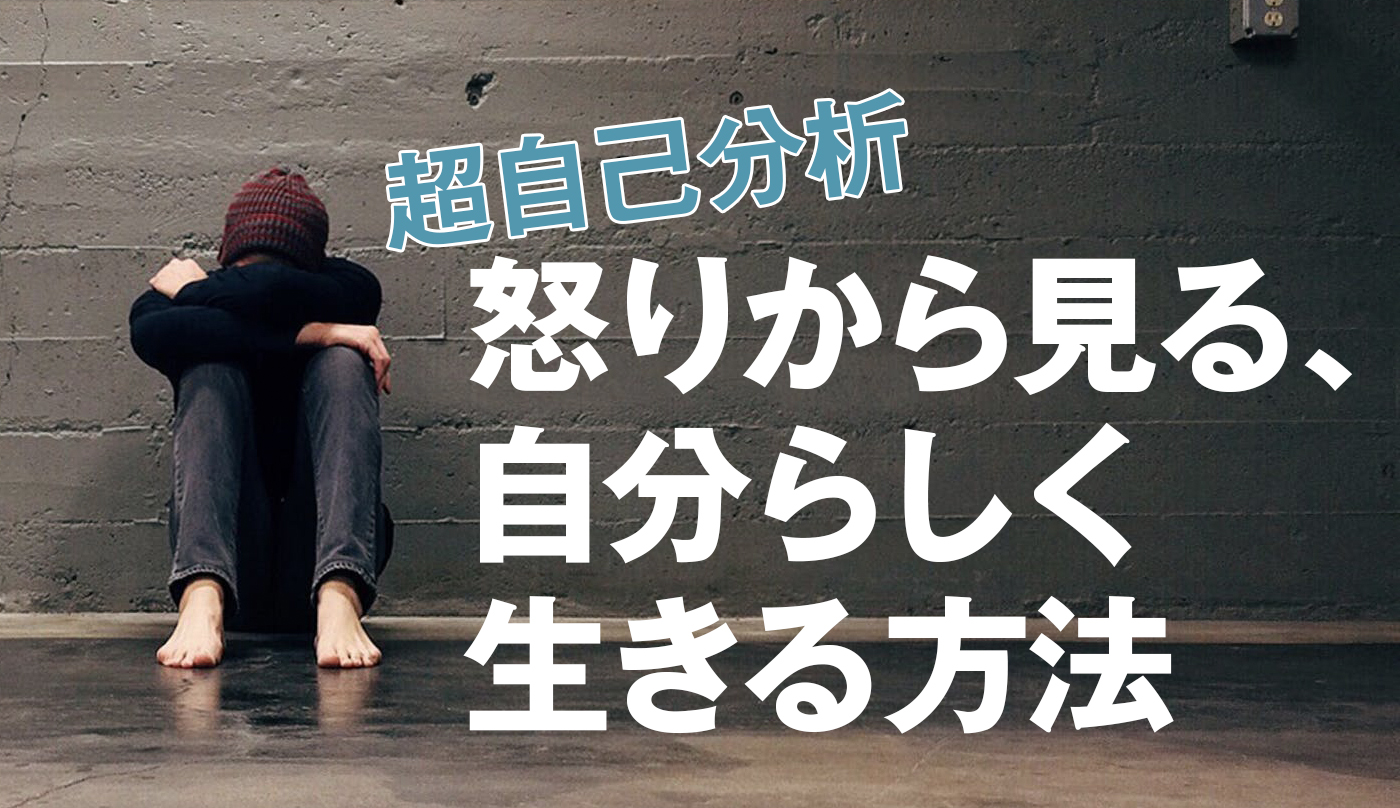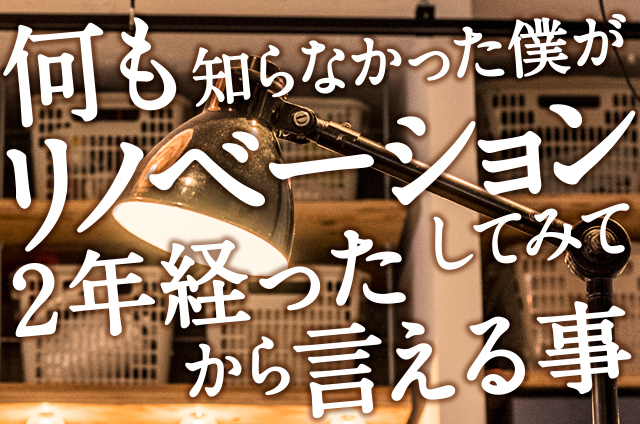一億総クリエイター時代に価値の高いクリエイターになるための条件

誰でも、ツイッター、フェイスブック、インスタ、YOUTUBE、ブログなどで作品を披露することができ、そこにフォロワー(評価)がつく今の時代は一億総クリエイター時代と言えると思う。(世界70億人でもあるが)
昔よりも明らかに皆が作品を作ってアウトプットしている。そうなると、価値の真価が問われるのがプロのクリエイターたち。
今、価値の高い多くの素人クリエイターが登場しているからです。
その人たちは必ずしもクリエイティブな業界の人達ではなく、自分の価値を世の中へ伝えるためにクリエイティブの力を使っているに過ぎないのです。
結果的に誰もがクリエイターになっている。
もくじ
下がるクリエイターの価値

僕はプロのクリエイターの価値は下がっていると感じています。
その理由は、大企業が広告を打つコストと効果よりも、エンゲージメント率の高いインフルエンサーがSNSでアウトプットした場合のコストパフォーマンスが圧倒的に高いからです。つまり個人のクリエイターが力を持つようになっているというわけ。
一般的なプロのクリエイターは企業の販促に関わることを生業としている場合が多く、広告、web、映像などの企業案件を広告代理店が請け負い、デザイナー、フォトグラファー、映像制作などの制作会社へ流れています。(企業と直接受けるパターンもある)
この業界ルートがクリエイターの価値を下げさせています。
例えば、A制作会社、B制作会社があった場合、どちらも満足な能力が持っていたとしたらどうなるか?
答えは、かかる費用が安い方を選びます。
半端なクリエイターは価値が下がり続けるのです。半端同士の価格破壊が起こるからです。
天才しか生き残れない
ということは、どうすれば良いかというと高くてもやってほしいクリエイターになれば良い。
しかし、ほとんどのクリエイターは凡人です。どんな業界でも天才(強烈な情熱を持っている人)は一部しかいないのは当然です。
業界にいると自分には絶対に超えられない壁を感じることがあると思います。僕はデザイン業界でそれを感じました。
自分には才能がないと諦めて凡人だと認めて脇役に徹して生きるしかないのか?
いや、そんなことはない、凡人が勝つ方法があります。
価値の高いクリエイターになる戦略を考えましょう。
希少性が価値を決めている
半端なプロのクリエイターは価値が下がり続けると思います。半端同士の価格破壊が起こるからです。
才能のある人は中央突破でいけます。凡人が勝つためには戦略を立てなければいけない。
脇役として割り切れるのか?それとも主役になるために必要とされる人間になるのか?弱者の戦略を考えよう。
— 好きなことで稼ぐ個人|タカシマ (@mrito1952) May 15, 2018
業界に就職できれば専門家(プロ)になることができます。経験を積んだ専門家は普通の人よりも技術と知識があり、しかも少数です。
希少=価値がある、という構造から専門家になりたい需要は高まります。
そのほかにも職種によってはその職業に就きたいと憧れる人たちからの需要も高まります。美容師業界、アパレル業界、デザイン業界などオシャレでカッコイイ感じの業界にはとくに希望者が殺到します。(しかも、これらの職業は設備費用も低く始めやすい。)
そうなると、専門家が溢れて希少性がなくなり価値は下がります。
そういう状況下では天才以外はみんな普通ということになりますので生き抜くのはとても厳しいのです。
その結果、自分は価値の低い人間だとついつい思ってしまう。
凡人に未来はない構造

デザイナーの場合はデザインの専門学校(または美大など)へ入り、卒業前には学校に届いているデザイン事務所の求人票(またはデザインの求人サイト)から就職をするというルートがあります。
これがデザイン業界の入り方です。デザイン業界に限らず、ほとんどの場合同じようなルートがあり、そのルートを使って大勢の中の一人になっていると思います。
僕はこの業界ルートを使うと狭い世界で自分に才能がないと勘違いをして埋もれてしまう可能性が高いと思っています。

自分が業界にいると、この先に何が起こるかというルートも見えてきます。
僕がいたデザイン業界は3年間頑張ってようやく一人前のデザイナーになることができると言われています。
一人前のデザイナーになり更に経験を積むとアートディレクターという上級職につくことができます。デザインも作りますが主に全体を判断・指示を行う仕事です。
更にその先にはクリエイティブディレクターというデザインにとどまらずコンセプトから設計をする仕事もあります。一部にはクライアントの社内クリエイティブディレクターというポジションもあったりします。
平社員から課長、課長から部長みたいな組織の構図と近いと思います。
この構造が何を意味するかというと能力がある一部の人以外に未来はないということです。
戦わないこと(戦略)が大事
https://twitter.com/taichinakaj/status/995680018037522439
天才と同条件で勝負するのはコストが大きすぎます。自分と同じような能力の人が多い場所で勝負するのもまたコストが大きい。凡人はいかにして効率よく成功するかということ(戦略)を考えなくてはいけません。
このツイートの優秀な美容師と戦わないで済むという言葉は戦略です。
もっというと自分の価値が響く場所を見つけて勝負することがとても重要なことだと思うのです。
業界を横断すると価値が生まれる
デザイン業界とアパレル業界に転職したことがあるんだけど常識が全く違ってた。
今まで常識だと思ったことが通用しなかったり、逆に圧倒的に優位になったりした。
業界内で転職繰り返しても何も起きない。新しい文化に身を投じると人生が変わる。
— 好きなことで稼ぐ個人|タカシマ (@mrito1952) May 3, 2018
僕は別の業界へ転職したことで自分の価値が変わった瞬間を経験をしたことがあります。
当時、自分が持っていたスキルはデザイン、アートディレクション、撮影知識などです。
販促関係のデザイナーとしてアパレル業界に転職しましたが、その業界ではデザインオペレーター(ソフトを使えて作業するだけの人)がいるのみで自分以外そのスキルを持った人がいませんでした。
そうなると自分の能力が有効でした。アパレルの写真撮影をして販促物に反映したり、デザインの作業効率をあげたりと、デザイン業界ではごくごく普通の仕事に価値がおび始めたのです。
結論、自分だけのブルーオーシャンを見つけること

今回の記事で何を言いたかったのかというと、自己スキルを理解して、その能力が必要な場所に自分を移動させるということです。
自分の能力がピッタリ合う業界はどこか?一つの業界にいるとそこ以外見えなくなってきます。
撮影スキルがある人はカメラマンの業界で勝負するのではなく自社で撮影が必要なメーカーに行くほうが賢いと思う。例えばアパレルメーカーの撮影の部署は人手不足の可能性があります。それは業界が違うので募集に人が集まらないからです。
能力は同じでも、業界の凡人になるか、需要のある場所を見つけて重宝されるか。
だから僕は人にオススメするのは、大勢の人に会って他の業界の話を聞きだすことです。
そして自分の居場所を見つけて自分の得意なことや好きなことで生きるんです。
大事なのは近い価値観の多様な人達が集まれること。情報共有することでお互いにメリットがあること。
そんな場を作ることにしました。
5/26satに都内某所で個人で生きるためのイベント「個人戦略論」を行います。(あと何席かしかないけど)
テーマはターゲット戦略とマネタイズの繋げ方について。